ゴールドスミスの提唱した自律分節音韻論のには、
連結線によって、音声と韻律を結びつける条件が提示されている。
これを適格性条件(well-formedness condition)と言い、4つの項目がある。
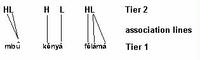
①全ての音調支持単位は音調を持つ。
②全ての音調は音調支持単位に連結する。
③連結は左から右の方向へ、一つずつ連結される。
④連結線は交差してはならない。
音調支持単位(tone-bearing unit)とは、音節や、アクセント核をもつ音の一塊を指す。
音調(tone)とは、音とは切り離された、韻律の変化である。
図ではHとLで表されている。
時間経過は、左から右へと流れて行くので、
この4つの項目は当然と考えられるし、前提ともいえる。
しかし、人間の認識はあまり信用できない。
④の、連結線の交差が起こると言うことは、音のユニットが、時間的に入れ替わることである。
人間は、目立つ音があると、周囲のより弱い音の認識能力が著しく低下すると言われている。
つまり、どの順番で音が発話されたかという知覚は、あまり正確ではない。
「ふいんき」「わずわらしい」「あがらう」「まぎわらしい」などなど、
慣習やいろんな要因によって知覚が惑わされることが多くある。
そして、OCP(obligate contour principle)とよばれる
「隣接するトーン要素は起伏を名なさなければならない(同一音調隣接の禁止)」の制約により、
HHやLLを禁止し、一つのHまたはLから、連結線が1本ないし複数本出る。
これにより、トーンの推移という考えを、
より分かりやすく説明することが出来るようになった。
参考文献
田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009
連結線によって、音声と韻律を結びつける条件が提示されている。
これを適格性条件(well-formedness condition)と言い、4つの項目がある。
①全ての音調支持単位は音調を持つ。
②全ての音調は音調支持単位に連結する。
③連結は左から右の方向へ、一つずつ連結される。
④連結線は交差してはならない。
音調支持単位(tone-bearing unit)とは、音節や、アクセント核をもつ音の一塊を指す。
音調(tone)とは、音とは切り離された、韻律の変化である。
図ではHとLで表されている。
時間経過は、左から右へと流れて行くので、
この4つの項目は当然と考えられるし、前提ともいえる。
しかし、人間の認識はあまり信用できない。
④の、連結線の交差が起こると言うことは、音のユニットが、時間的に入れ替わることである。
人間は、目立つ音があると、周囲のより弱い音の認識能力が著しく低下すると言われている。
つまり、どの順番で音が発話されたかという知覚は、あまり正確ではない。
「ふいんき」「わずわらしい」「あがらう」「まぎわらしい」などなど、
慣習やいろんな要因によって知覚が惑わされることが多くある。
そして、OCP(obligate contour principle)とよばれる
「隣接するトーン要素は起伏を名なさなければならない(同一音調隣接の禁止)」の制約により、
HHやLLを禁止し、一つのHまたはLから、連結線が1本ないし複数本出る。
これにより、トーンの推移という考えを、
より分かりやすく説明することが出来るようになった。
参考文献
田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009
PR
この記事にコメントする
言語学が大好きな一般人のブログです。
過去の記事は、軌跡として残しておきます。
カレンダー
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
ブログ内検索
カテゴリー
最新記事
(10/02)
(09/30)
(09/29)
(09/26)
(09/25)
プロフィール
HN:
てぬ
性別:
女性
自己紹介:
大学院で言語学を学びたい大学生が、日々の勉強の成果を記録してゆく為の、個人サイトでした。
最新トラックバック
最古記事
(01/01)
(04/07)
(04/08)
(04/09)
(04/09)
P R

