規則と規則の関係性の研究は、さらに深い考察へと進む。
ポール・キパルスキーとK. P. モハナンらによって、
音韻規則を分類する、語彙音韻論(lexical phonology)が発展した。
これは、規則の順序の可能性を制限する理論である。
つまり、同化、削除、異音、挿入など、n個の規則が関係した音韻変化では、
その規則の適応順序は、nの階乗だけ種類がある。
そこで、語彙形成レベルで規則を二つに分類し、
基本的に、語彙形成以前の規則は、語彙形成以後の規則より先行する、という仮説を立てた。
これで、順序の可能性が大幅に減るのである。
語彙音韻論では以下のような出力モデルがある。
基底レベル
↓
語彙規則(lexical rule)
↓
語彙レベル
↓
後語彙規則(post-lexical rule)
↓
表層レベル
↓
音声実行規則(phonetic implementation rule)
↓
調音・発声・知覚
音韻論が扱うのは、基底レベルから表層レベルまでである。
それ以降は音声学の分野となる。
音声実行規則とは、歯痛や鼻づまりなど、様々な障害があっても
最大限に音韻体系を守ろうと修正するものである。
具体的な説明の前に、まず音節(syllable)の説明をする。
音節とは、母音を核(nucleus)として成る、音素の単位である。
音節の境界は言語によって違い、話者の直感に頼る部分も多い。
日本語のひらがな・カタカナは基本的に、一文字一音節である。
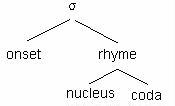
図のように、
核は、音節の最後の要素である末音(coda)と結びついて脚韻(rhyme)を成す。
頭音(onset)は核の前の子音群である。
日本語「か」のように、頭音と核でなり、
脚韻を構成しない音節を軽音節(right syllable)といい、
母音で終わり、末音のない音節を開音節(open syllable)と言う。
一方、英語の"strong"のような、
核と末音で脚韻を構成する音節を重音節(heavy syllable)といい、
子音で終わり、末音のある音節を閉音節(closed syllable)と言う。
参考文献
田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009
「Glossary of liguistics terms "What is a syllable?"」
ポール・キパルスキーとK. P. モハナンらによって、
音韻規則を分類する、語彙音韻論(lexical phonology)が発展した。
これは、規則の順序の可能性を制限する理論である。
つまり、同化、削除、異音、挿入など、n個の規則が関係した音韻変化では、
その規則の適応順序は、nの階乗だけ種類がある。
そこで、語彙形成レベルで規則を二つに分類し、
基本的に、語彙形成以前の規則は、語彙形成以後の規則より先行する、という仮説を立てた。
これで、順序の可能性が大幅に減るのである。
語彙音韻論では以下のような出力モデルがある。
基底レベル
↓
語彙規則(lexical rule)
↓
語彙レベル
↓
後語彙規則(post-lexical rule)
↓
表層レベル
↓
音声実行規則(phonetic implementation rule)
↓
調音・発声・知覚
音韻論が扱うのは、基底レベルから表層レベルまでである。
それ以降は音声学の分野となる。
音声実行規則とは、歯痛や鼻づまりなど、様々な障害があっても
最大限に音韻体系を守ろうと修正するものである。
具体的な説明の前に、まず音節(syllable)の説明をする。
音節とは、母音を核(nucleus)として成る、音素の単位である。
音節の境界は言語によって違い、話者の直感に頼る部分も多い。
日本語のひらがな・カタカナは基本的に、一文字一音節である。
図のように、
核は、音節の最後の要素である末音(coda)と結びついて脚韻(rhyme)を成す。
頭音(onset)は核の前の子音群である。
日本語「か」のように、頭音と核でなり、
脚韻を構成しない音節を軽音節(right syllable)といい、
母音で終わり、末音のない音節を開音節(open syllable)と言う。
一方、英語の"strong"のような、
核と末音で脚韻を構成する音節を重音節(heavy syllable)といい、
子音で終わり、末音のある音節を閉音節(closed syllable)と言う。
参考文献
田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009
「Glossary of liguistics terms "What is a syllable?"」
PR
語彙規則と後語彙規則の違いは以下の六つである。
規則適応後に生じる音が、音素内に収まっているかと言う問題は、
特に、語彙規則と後語彙規則を区別する大きな原理である。
これを構造保持(structual preservation)と言う。
音素対立の中和や、子音の無声化など、
特定の言語が持つ音素体系の中での変化は、構造保持があり、語彙規則である。
一方、異音変化や英語で見られる曖昧母音などは、
その言語の音素ではない音に変化するため、構造保持が無く、後語彙規則である。
その次は、適応語種である。
語種とは、固有語、借用語などの区別である。
日本語には、和語、漢語、外来語と、それらが混ざった混種語があるとされる。
連濁などは和語にしか適応されない。
連濁のように適応語種を選ぶものが、語彙規則である。
異音規則のように、語種に依らず自動的に適応されるものが、後語彙規則である。
05/27で述べた、随意性も大きな目安になる。
世代や性格など、話者による個体差が無く、
会話のスタイルに左右されないものが、語彙規則である。
「すごい」→「すげー」の母音融合など、
個体差があり、発話のスピードなどに影響されやすいものが、後語彙規則である。
これと同時に、単語を越えた変化も生じる。
通常語彙規則として、単語内で生じる鼻音同化は、
単語を越え、超分節的に、後語彙規則として生じることがある。
英語の単語では、"impossible"のように、"p"の前の鼻音は"m"である。
しかし、話者によっては、"in Paris"も、"im Paris"と発音することがある。
これが単語を越えた、鼻音同化である。
最後の違いは、例外の有無である。
語彙目録としての深い部分に関わる語彙規則には、個別的な例外が多い。
和語の連濁も、「味噌汁」(cf.「だし汁」)や「夏草」(cf.「野草」)などの例外がある。
一方、より広範囲に、随意的に生じる後語彙規則は、
まんべんなく適応され例外が少ない。
これら六つの性質は、全てが綺麗に二されるわけではないが、
音韻規則にも性質の分類が可能であると言う考えは、
さらなる細かい区分を生み出した。
また、先に述べたように、後語彙規則は音声学と隣接しているが、
音韻論はあくまで、抽象的体系の文法の範囲で、
音韻規則を扱っているということが、明確な音声学との境界線であるといえる。
参考文献
田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009
規則適応後に生じる音が、音素内に収まっているかと言う問題は、
特に、語彙規則と後語彙規則を区別する大きな原理である。
これを構造保持(structual preservation)と言う。
音素対立の中和や、子音の無声化など、
特定の言語が持つ音素体系の中での変化は、構造保持があり、語彙規則である。
一方、異音変化や英語で見られる曖昧母音などは、
その言語の音素ではない音に変化するため、構造保持が無く、後語彙規則である。
その次は、適応語種である。
語種とは、固有語、借用語などの区別である。
日本語には、和語、漢語、外来語と、それらが混ざった混種語があるとされる。
連濁などは和語にしか適応されない。
連濁のように適応語種を選ぶものが、語彙規則である。
異音規則のように、語種に依らず自動的に適応されるものが、後語彙規則である。
05/27で述べた、随意性も大きな目安になる。
世代や性格など、話者による個体差が無く、
会話のスタイルに左右されないものが、語彙規則である。
「すごい」→「すげー」の母音融合など、
個体差があり、発話のスピードなどに影響されやすいものが、後語彙規則である。
これと同時に、単語を越えた変化も生じる。
通常語彙規則として、単語内で生じる鼻音同化は、
単語を越え、超分節的に、後語彙規則として生じることがある。
英語の単語では、"impossible"のように、"p"の前の鼻音は"m"である。
しかし、話者によっては、"in Paris"も、"im Paris"と発音することがある。
これが単語を越えた、鼻音同化である。
最後の違いは、例外の有無である。
語彙目録としての深い部分に関わる語彙規則には、個別的な例外が多い。
和語の連濁も、「味噌汁」(cf.「だし汁」)や「夏草」(cf.「野草」)などの例外がある。
一方、より広範囲に、随意的に生じる後語彙規則は、
まんべんなく適応され例外が少ない。
これら六つの性質は、全てが綺麗に二されるわけではないが、
音韻規則にも性質の分類が可能であると言う考えは、
さらなる細かい区分を生み出した。
また、先に述べたように、後語彙規則は音声学と隣接しているが、
音韻論はあくまで、抽象的体系の文法の範囲で、
音韻規則を扱っているということが、明確な音声学との境界線であるといえる。
参考文献
田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009
側面摩擦音(lateral fricative)と中線的摩擦音の違いは、調音時の舌の形にある。
中線的摩擦音はその名の通り、
口の中をまっすぐに空気が通過するように
舌の縁側が上歯茎に触れ、通り道を制限している。
側面的摩擦音は、舌が上歯茎や硬口蓋の中央に振れ、
呼気が、奥の歯茎と舌の縁側の狭い隙間を勢いよく通過し、
摩擦音が生じる。
主な側面摩擦音は、以下の二つである。
[ ɬ ] 無声歯茎側面摩擦音(voiceless alveolar lateral fricative)
[ ɮ ] 有声歯茎側面摩擦音(voiced alveolar lateral fricative)
口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断するとともに、
舌端と上前歯茎で閉鎖を作り、
その触れている両脇の狭い隙間に呼気を通し、発声する。
声帯の振動がなければ[ ɬ ]、振動を伴えば[ ɮ ]。
南アフリカのズールー語や、モンゴル、カフカスの言語でみられる。
参考文献
斉藤純男 『日本語音声学入門 改訂版』 三省堂 2008
中線的摩擦音はその名の通り、
口の中をまっすぐに空気が通過するように
舌の縁側が上歯茎に触れ、通り道を制限している。
側面的摩擦音は、舌が上歯茎や硬口蓋の中央に振れ、
呼気が、奥の歯茎と舌の縁側の狭い隙間を勢いよく通過し、
摩擦音が生じる。
主な側面摩擦音は、以下の二つである。
[ ɬ ] 無声歯茎側面摩擦音(voiceless alveolar lateral fricative)
[ ɮ ] 有声歯茎側面摩擦音(voiced alveolar lateral fricative)
口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断するとともに、
舌端と上前歯茎で閉鎖を作り、
その触れている両脇の狭い隙間に呼気を通し、発声する。
声帯の振動がなければ[ ɬ ]、振動を伴えば[ ɮ ]。
南アフリカのズールー語や、モンゴル、カフカスの言語でみられる。
参考文献
斉藤純男 『日本語音声学入門 改訂版』 三省堂 2008
側面接近音(lateral approximant)は、
側面摩擦音と同じような調音方法で、
調音器官の隙間を広く取り、阻害の程度は低く摩擦音は生じない。
中線的接近音と同様に、主に有声音である。
[ l ] 有声歯茎側面接近音(voiced alveolar lateral approximant)
口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、
舌端と歯茎で閉鎖を作り、
その両脇が接近した状態で、発声する。
英語、フランス、イタリア語、スペイン語などの" l "の音であり、
多くの言語にみられる。
[ ɭ ] 有声そり舌側面接近音(voiced retroflex lateral approximant)
口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、
舌尖と後部歯茎で閉鎖を作り、
その両脇が接近した状態で、発声する。
朝鮮語やインド系の言葉にみられる。
[ ʎ ] 有声硬口蓋側面接近音(voiced palatal lateral approximant)
口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、
前舌と硬口蓋で閉鎖を作り、
その両脇が接近した状態で、発声する。
イタリア語やスペイン語でみられる。
[ ʟ ] 有声軟口蓋側面接近音(voiced velar lateral approximant)
口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、
後舌と軟口蓋で閉鎖を作り、
その両脇が接近した状態で、発声する。
パプアニューギニアの言葉などで見られるが、あまり一般的ではない。
参考文献
斉藤純男 『日本語音声学入門 改訂版』 三省堂 2008
側面摩擦音と同じような調音方法で、
調音器官の隙間を広く取り、阻害の程度は低く摩擦音は生じない。
中線的接近音と同様に、主に有声音である。
[ l ] 有声歯茎側面接近音(voiced alveolar lateral approximant)
口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、
舌端と歯茎で閉鎖を作り、
その両脇が接近した状態で、発声する。
英語、フランス、イタリア語、スペイン語などの" l "の音であり、
多くの言語にみられる。
[ ɭ ] 有声そり舌側面接近音(voiced retroflex lateral approximant)
口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、
舌尖と後部歯茎で閉鎖を作り、
その両脇が接近した状態で、発声する。
朝鮮語やインド系の言葉にみられる。
[ ʎ ] 有声硬口蓋側面接近音(voiced palatal lateral approximant)
口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、
前舌と硬口蓋で閉鎖を作り、
その両脇が接近した状態で、発声する。
イタリア語やスペイン語でみられる。
[ ʟ ] 有声軟口蓋側面接近音(voiced velar lateral approximant)
口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、
後舌と軟口蓋で閉鎖を作り、
その両脇が接近した状態で、発声する。
パプアニューギニアの言葉などで見られるが、あまり一般的ではない。
参考文献
斉藤純男 『日本語音声学入門 改訂版』 三省堂 2008
これまで述べてきたの8個の調音方法、
破裂音、鼻音、ふるえ音、はじき音、
摩擦音、接近音、側面摩擦音、側面接近音が、
IPAの大きな表(肺臓気流)に記載されているものである。
今回は、この表にはない、欄外の「その他の記号」について述べる。
[ ʜ ] 無声喉頭蓋摩擦音(voiceless epiglottis fricative)
[ ʢ ] 有声喉頭蓋摩擦音(voiced epiglittis fricative)
口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、
喉頭蓋と咽頭壁で狭い隙間を作り、発声する。
側面的調音は生理的に不可能である。
声帯の振動が無ければ[ ʜ ]、振動を伴えば[ ʢ ]。
カフカスのアヴァール語などに見られ、
アラビア語の咽頭音の変種として見られることもある。
[ ʡ ] 喉頭蓋破裂音(epiglottis plosive)
口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、
喉頭蓋と咽頭壁で閉鎖、開放を行って発声する。
ここでの有声音、鼻音は生理的に不可能とされている。
摩擦音と同じように、カフカス地方で見られる。
[ ɕ ] 無声歯茎硬口蓋摩擦音(voiceless alveolo-palatal fricative)
[ ʑ ] 有声歯茎硬口蓋摩擦音(voiced alveolo-palatal fricative)
口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、
舌端と、歯茎から硬口蓋の広い範囲で狭い隙間を作り、発声する。
ふたつの調音位置で調音するものを二重調音というが、極端な例は別枠で述べる。
声帯の振動が無ければ[ ɕ ]、振動を伴えば[ ʑ ]。
日本語の「し」「しゃ」「しゅ」「しょ」「じ」「じゃ」「じゅ」「じょ」、
韓国語、中国語などでみられる。
[ ɺ ] 有声歯茎側面はじき音(voiced alveolar lateral flap)
口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、
舌端と歯茎で閉鎖をつくり、
その両脇を軽く弾ませるように調音する。
歯茎側面接近音[ l ]を短く発音したような音声である。
日本語のラ行子音に近く、タンザニアのチャガ語に見られる。
長い" r "を上下逆さまにした記号である。
参考文献
斉藤純男 『日本語音声学入門 改訂版』 三省堂 2008
破裂音、鼻音、ふるえ音、はじき音、
摩擦音、接近音、側面摩擦音、側面接近音が、
IPAの大きな表(肺臓気流)に記載されているものである。
今回は、この表にはない、欄外の「その他の記号」について述べる。
[ ʜ ] 無声喉頭蓋摩擦音(voiceless epiglottis fricative)
[ ʢ ] 有声喉頭蓋摩擦音(voiced epiglittis fricative)
口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、
喉頭蓋と咽頭壁で狭い隙間を作り、発声する。
側面的調音は生理的に不可能である。
声帯の振動が無ければ[ ʜ ]、振動を伴えば[ ʢ ]。
カフカスのアヴァール語などに見られ、
アラビア語の咽頭音の変種として見られることもある。
[ ʡ ] 喉頭蓋破裂音(epiglottis plosive)
口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、
喉頭蓋と咽頭壁で閉鎖、開放を行って発声する。
ここでの有声音、鼻音は生理的に不可能とされている。
摩擦音と同じように、カフカス地方で見られる。
[ ɕ ] 無声歯茎硬口蓋摩擦音(voiceless alveolo-palatal fricative)
[ ʑ ] 有声歯茎硬口蓋摩擦音(voiced alveolo-palatal fricative)
口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、
舌端と、歯茎から硬口蓋の広い範囲で狭い隙間を作り、発声する。
ふたつの調音位置で調音するものを二重調音というが、極端な例は別枠で述べる。
声帯の振動が無ければ[ ɕ ]、振動を伴えば[ ʑ ]。
日本語の「し」「しゃ」「しゅ」「しょ」「じ」「じゃ」「じゅ」「じょ」、
韓国語、中国語などでみられる。
[ ɺ ] 有声歯茎側面はじき音(voiced alveolar lateral flap)
口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、
舌端と歯茎で閉鎖をつくり、
その両脇を軽く弾ませるように調音する。
歯茎側面接近音[ l ]を短く発音したような音声である。
日本語のラ行子音に近く、タンザニアのチャガ語に見られる。
長い" r "を上下逆さまにした記号である。
参考文献
斉藤純男 『日本語音声学入門 改訂版』 三省堂 2008
言語学が大好きな一般人のブログです。
過去の記事は、軌跡として残しておきます。
カレンダー
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
ブログ内検索
カテゴリー
最新記事
(10/02)
(09/30)
(09/29)
(09/26)
(09/25)
プロフィール
HN:
てぬ
性別:
女性
自己紹介:
大学院で言語学を学びたい大学生が、日々の勉強の成果を記録してゆく為の、個人サイトでした。
最新トラックバック
最古記事
(01/01)
(04/07)
(04/08)
(04/09)
(04/09)
P R

